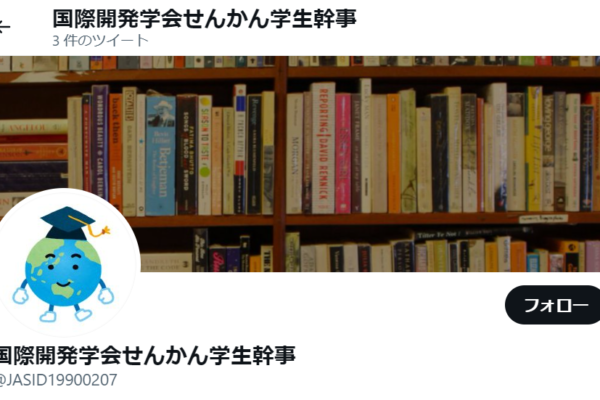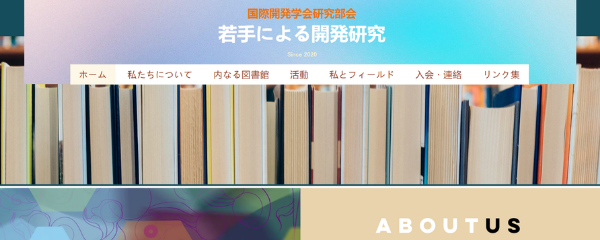[終]地方展開委員会

Regional Engagement
日本の地域づくりと世界の地域づくりをつなぐ
地方展開委員会は、(1)地方在住学会員の学会活動におけるニーズを開拓する、(2)社会実装委員会、人材育成委員会、広報委員会等他の委員会や地方支部と連携しながら地方在住の学会員の学会活動の充実化をはかるための各種企画を検討する、(3)地方在住の学会員のネットワーク化をはかり、将来的には未開催地域や条件不利地での地方大会開催やスタディツアー、エクスカーションの実施につながるような素地を築く、(4)地方に散在している開発に関心がある人々を発掘し激励し可能であれば会員になってもらい、日本の開発研究をもりあげるための仕掛けを考える、を活動目標に掲げています。
- 委員長:佐野麻由子(福岡県立大学)
- 幹事:生方史数(岡山大学)、梶英樹(高知大学)、木全洋一郎(国際協力機構、現在陸前高田市出向)、工藤尚悟(国際教養大学)、辰己佳寿子(福岡大学)、林裕(福岡大学)
出前講座 2022
出前講座の目的は、(1)地方在住学会員、留学生会員と他の学会員の交流を促進すること、(2)国際協力や開発に関心をもつ非学会員と国際開発学会との接点をつくり日本の国際開発にかかわる教育と研究の裾野を広げることです。
出前講座の募集を開始しました!
2022年度は会員限定で行いますが、会員が責任をもって仲介していただける場合は、非会員の所属する団体での実施も可能です(会員の方がお申し込みください)。
<講師派遣依頼の流れ>
1)依頼側は、申込書にご記入の上、実施予定日の1ヵ月前までにEメールで地方展開委員会に申し込む(原則、講師派遣に係わる費用は依頼側の負担)。申し込み先:regional.engagement★gmail.com(★を@に変更してください。)
出前講座申込用紙
2)地方展開委員会が、申込書に書かれた希望の講師に打診をする。
3)快諾が得られたら、講師と申込者が、直接やりとりをし、詳細等を打ち合わせる。
4) 実施後、依頼側は、実施報告書を3週間以内にEメールで地方展開委員会に提出する。
実施報告書
5) 実施後、講師は、講座の概要について学会のニュースレター・HPに掲載するための600字程度の報告を3週間以内にEメールで地方展開委員会に提出する(様式自由)。
<留意事項>
・費用(旅費・謝金等)は原則として依頼側のご負担となります。経費に限りがある場合には、国際開発学会からの補助(1講義5千円)を利用できます。
・地方展開委員会は、派遣業務ではなく人材バンクとしての仲介的な役割を担っています。当事者間のトラブル対応や講義内容の質の保証はいたしかねますのであらかじめご了承ください。
出前講座講師リスト
講師リスト詳細(PDF)
| 名前 | 所属等 | 専門分野 | 講義タイトル | ||
| 北海道 | 1 | 木全 洋一郎 | JICA北海道 (帯広) |
ガバナンス・地方行政 | 途上国と日本のまちづくり協力 |
| 東 北 地 方 |
2 | 安部 雅人 | 東北大学復興農学マイスター・IT農学マイスター/尚絅学院大学 | 国際流通論/国際エネルギー資源論/国際政治学 | 【講義1】 SDGs(持続可能な開発目標)の時代における新しい「流通論」 |
| 3 | 【講義2】アジア太平洋地域における国際政治経済の重心の変容―中国の「一帯一路」構想と米国の「米国第一主義」構想を中心に― | ||||
| 4 | 工藤 尚悟 |
国際教養大学国際教養学部グローバル・スタディズ領域 | サステイナビリティ学、地域づくり(秋田と南アフリカ) | 私たちのサステイナビリティ – 地域からSDGsを問い直す | |
| 関 東 地 方 |
5 | 伏見 勝利 | JICA緒方研究所 | プロジェクトマネジメント | 複雑な開発協力プロジェクトの事業管理手法 |
| 6 | 朽木 昭文 |
放送大学 | 産業集積、アジア経済、開発経済学 | 【講義1】 産業集積による地域開発 | |
| 7 | 【講義2】アジアにおける産業集積による地域開発 | ||||
| 8 | 栗原 俊輔 | 宇都宮大学 国際学部 |
ガバナンス、組織開発、南アジア | 国際協力における市民参加 | |
| 9 | 岡野内正 | 法政大学 社会学部 |
国際協力論、国際政治経済学、社会理論、中東研究、環境社会学、村落研究 | 【講義1】 SDGs達成を真剣に考える――それどころではない世の中の仕組みを変えるために | |
| 10 | 【講義2】人類遺産資本主義論 | ||||
| 11 | 米原 あき | 東洋大学 | 人間開発政策の評価、比較教育学、プログラム評価論、社会調査、社会統計 | SDGs/ESDの評価:見えない価値を引き出すしくみ | |
| 関 西 地 方 |
12 | 田中 樹 |
摂南大学農学部 食農ビジネス学科 |
地域開発論、環境農学 | 【講義1】 西アフリカ半乾燥地での砂漠化問題と実践的な対処方法 |
| 13 | 【講義2】東アフリカの山間地でのスパイス栽培:人びとの暮らしと生態系保全の両立 | ||||
| 中 国 地 方 |
14 | 朝倉 隆道 |
広島大学教育開発国際協力研究センター(CICE) | 国際教育開発論、教育社会学 | 国際教育協力における変容:民間企業を中心とした非政府アクターの台頭 |
| 15 | 生方 史数 | 岡山大学大学院 生命科学研究科 |
東南アジア地域研究、ポリティカル・エコロジー | 環境保全は社会をどうつくりかえるか?自然保護の現場から | |
| 四 国 地 方 |
16 | 梶 英樹 |
高知大学 次世代地域創造センター |
地域連携、NPO/NGO論 | 大学と地域との連携を推進するコーディネーションの実践 |
| 17 | 柴﨑 三郎 |
讃陽堂松原病院/香川大学医学部非常勤講師 | 国際医療協力/プライマリ・ケア | 援助のピットフォール | |
| 九 州 地 方 |
18 | 林 裕 |
福岡大学 商学部 |
開発研究、アフガニスタン、平和構築、国際政治 | グッド・イナフ・ガバナンス:紛争から立ち直る国に、国際社会は何を求めるのか? |
| 19 | 佐野 麻由子 |
福岡県立大学 人間社会学部 |
社会学、ジェンダー、ネパール地域研究 | ベッカ、タヤニオル、メグリチボク:比較社会学入門 | |
| 20 | 辰己 佳寿子 |
福岡大学 経済学部 |
農村社会学 | グローカルな絆が生まれる瞬間-支援する側/される側の互いが成長する相互多重型支援 |
出前講座2021
<出前講座@国際教養大学「人口関係論」(講義担当者:工藤尚悟)>
〇開講日:2021年9月24日
〇講座タイトル:「高知県嶺北地域における関係性に着目した山村移住者による地域づくり事例」
〇講師:梶英樹(高知大学次世代地域創造センター地域コーディネーター)
<出前講座@高知県立嶺北高等学校 (講座のコーディネーター:梶英樹)>
〇開講日:2021年9月29日(水)13時30分~15時20分 (14:20~30分は10分休憩)
〇講座タイトル:「私たちのサステイナビリティ – 嶺北地域で何をサステイナブルにする?」
〇講師:工藤尚悟(国際教養学部グローバルスタディズ課程准教授)
〇場所:高知県県立嶺北高校 視聴覚室
〇実施方法:対面及びオンライン配信のハイブリッド方式
(視聴覚室にて対面講座を実施し、その他の生とは、各教室の電子黒板にてオンライン視聴)
〇受講者及び人数:嶺北高校の全校生徒1~3年 100名程度
〇受け入れ窓口:一般社団法人れいほく未来創造協議会・岡田様 嶺北高校・田邊先生
〇スケジュール12:00出発 車で宿泊先までお迎え→ 嶺北高校へ向けて出発
13:00-13:30 嶺北高校に到着、準備・打ち合わせ
13:30-14:20 (50分) 出前講座14:20-14:30 (10分) <休憩>
14:30-15:20 (50分) 出前講座
15:50ごろから17:00ごろ 一般社団法人れいほく未来創造協議会・岡田様と面会、意見交換
嶺北高校生徒寮も視察


【第2日目:視察】
〇日時:9月30日(木)10時00分~16時30分
〇スケジュール
8:30- ホテルにお出迎え → 大豊町に向けて出発
10:00-12:00 バレチオ・バイオレットさん訪問(大豊町豊永地区)
12:00-13:00 (昼食:近藤ストアー)、
13:30-14:30 ビノッド・プラサード・グプタさん面会
14:30-16:00 豊永郷民族博物館・定福寺 釣井さん訪問(大豊町豊永地区)
16:30-17:15 高知龍馬空港へ移動
19:00発 高知→東京
9/30 視察訪問先(嶺北への移住者)関連情報
①大豊町豊永地区:バレチオ・バイオレットさん訪問
投資会社の出身で、海外に幅広いネットワークを持っており、移住後、海外に大豊町をメディア
発信されたり、地域でのビジネスの可能性を見出してフィットネス施設の建設を進めている。
②永渕食堂 Shanti(ビノッド・プラサード・グプタさん)
インド出身で、大豊町に移住されて永渕地区でカレー店を開業している。グプタさんは、国の重
要無形民俗文化財に指定された「岩原・永渕神楽」の保存活動をされています。
③大豊町豊永地区:豊永郷民族博物館・定福寺 釣井さん
ローカル視点として、釣井さんは大豊町の歴史にも詳しい方で民族博物館も地域で運営されて
る。
〇豊永郷民族資料館HP
http://jofukuji-kochi.jp/museum_1.html
<出前講座@福岡県立大学「国際協力論」(講義担当者:佐野麻由子)>
〇開講日:2021年12月13日
〇講座タイトル:「『誰ひとり取り残さない』?-アフガニスタンを事例に」
〇講師:林裕(福岡大学商学部)


<出前講座@福岡県立大学「国際協力論」(講義担当者:佐野麻由子)>
〇開講日:2022年1月24日
〇講座タイトル:「岩手・陸前高田のポスト復興まちづくりから問い直す国際協力のあり方」
〇講師:木全洋一郎(陸前高田市地域振興部商政課課長/JICA)


都道府県別会員の分布(2020年12月末のデータ)
都道府県別の会員数をみると、東京が547人と最も多く(全体の36.5%)、次いで、神奈川(144人)、愛知(88人)、千葉(81人)です。会員5人以下の県は、熊本、佐賀、秋田、三重、鹿児島、福井です。山形県には会員がいません。